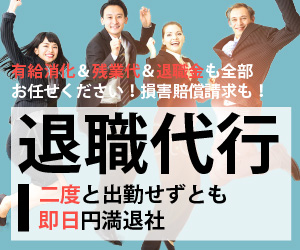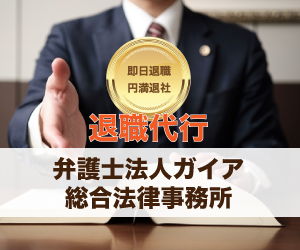退職代行サービスの選び方

※当サイトはスポンサーリンク広告を含んでいます。
当サイトにお越しいただきありがとうございます。
このサイトは私の経験も含めて、きちんと会社や事業所をやめるにあたって注意することや、退職代行を利用する際の注意点などをご紹介しようと思います。

退職代行サービスとは
退職代行サービスは、退職を希望する人に代わって会社に退職の意思を伝え、業務の必要な調整、退職金などの請求、離職票などの書類の発給を依頼してもらう総合サービスです。
こんな方が利用しています
人がいないからと会社を辞めると言い出せなかったり、上司や管理職からのハラスメント(いやがらせ)に悩んでいたり、夜間休日を問わずLINEやメールで指示が来て休まる暇がなかったり、いつも引き止めがあってやめられないと悩んでいる人などが利用することで、確実に辞められるようにしてもらえます。

今の時代、仕事が合わなかったり、人間関係の耐え難いストレスを受けることなど、その対応として需要が増えています。
どうしても退職したくて悩んでいるのなら、退職代行サービスを利用することはずるいことでも恥ずかしいことでもありません。
心身ともにおかしくなる前に、退職代行サービスに相談してみてください。
依頼した後は、あなたは一切会社とかかわる必要はありません。全部退職代行サービスでやってくれます。
退職代行サービスでできること
退職代行サービスでは、退職に伴う次のようなことを処理してくれます。
・退職意思を伝える
・会社との連絡調整
・退職書類の作成
・業務の引継ぎ調整
・有給休暇の消化
・退職日の調整
・離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票などの請求
・私物の引き取り
・貸与品の返却
・残業代の請求
・未払い金の請求
・退職金の請求
・慰謝料(損害賠償)の請求(弁護士のみ)
・訴訟の対応(弁護士のみ)
・社宅交渉
・サポート
・転職サポート(労働組合のみ)
※弁護士が行う退職代行と労働組合が行う退職代行では、主に訴訟関係で違いがあります。
今とても需要がありますから多くの退職代行がありますね。
どのような退職代行サービスを選択したらいいのか、詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧になってください。
退職代行サービスの法的根拠
退職代行は、依頼者に代わって企業と退職の交渉をするのですが、「代理交渉」は普通の民間企業ではできません。それは弁護士法があるためです。
民間企業が退職代行サービスを行っているケースがありますが、交渉を行うと弁護士法に抵触しますから、退職の意思を伝えるだけしかできません。
弁護士監修となっていても弁護士が表に出てくるわけではありません。
このため退職代行は弁護士が行うことが多いのですが、どうしても料金が高額になりがちです。
ところが、弁護士以外でも、ある団体は退職代行に関しては法的に交渉ができるのです。
それが「労働組合」です。
労働組合のメリットは料金が弁護士よりはずっと安価なことです。労働組合が運営する退職代行サービスの利用者は多いです。
労働組合が企業などと「交渉」できる根拠は、主に労働組合法に基づいています。
労働組合法第6条では、労働者が労働条件に関して団体交渉を行う権利が保障されています。これにより、労働組合は労働者の代理として企業と交渉することができるのです。
ただし継続的な細かな交渉や訴訟に発展しそうな特殊な場合は弁護士さんでないとできませんから、ここは注意しておいてください。
弁護士が行う退職代行サービス
普通に円満に会社を辞めたいだけなら、労働組合が行う退職代行サービスで十分対応可能ですが、次のようなトラブルがあって会社を辞めたいときは弁護士に依頼する方が良いと思います。

弁護士に依頼する方がいい場合
1.上司や経営者などからモラハラやセクハラなどを受けていて、場合によっては慰謝料を請求しようと思っている場合
2.長時間労働や過大なノルマなどを夜間休日を問わず高圧的に押し付けるブラック企業の場合
3.不誠実な企業で退職金の請求や有給消化の交渉などが難しい場合
4.会社から借入金があったり、いやがらせ的に損害賠償をちらつかせる場合
これらは例の一つです。話がこじれそうな場合は、弁護士でなければ対応がむずかしいですから、弁護士が行う退職代行サービスに依頼しましょう。
弁護士の退職代行サービスの内容
次の一覧をご覧ください。
| 項目 | 弁護士が行う退職代行 |
| 退職意思を伝える | 〇 |
| 会社との細かな連絡調整 | 〇 細かな調整に何度も対応できる |
| 退職書類の作成 | 〇 会社の指定された様式で作成できる |
| 業務の細かな引継ぎ調整 | 〇 細かな調整に対応できる |
| 有給休暇の消化 | 〇 |
| 退職日の調整 | 〇 意思を伝えるだけでなく日程の交渉ができる |
| 私物の引き取り・貸与品の返却 | 〇 |
| 残業代の請求 | 〇 弁護士の得意分野です |
| 未払い金の請求 | 〇 弁護士の得意分野です |
| 退職金の請求 | 〇 弁護士の得意分野です |
| 慰謝料(損害賠償)の請求 | 〇 弁護士の得意分野です |
| 訴訟の対応 | 〇 弁護士の得意分野です |
弁護士が出てくること自体で、会社は法外なことを言いにくいものです。会社側は、適当なことを言わせないという、ある種の圧力を感じます。
法律を盾にして退職希望者の側に立って有利に交渉を行ってもらえます。
ただ、弁護士は弁護士以外の担当者に指示して代理業務をさせることができませんから、弁護士本人が動く必要があり、スケージュールが過密なことがあります。
今日言って今日辞めたいとか、すべての課題を今日解決してほしいといったことが難しいです。
込み入った状況の場合は、事前に電話で相談が必要な場合があります。
そのような事情があることをあらかじめ承知しておいてください。
弁護士の退職代行サービスの料金
弁護士が行う退職代行サービスの料金の相場は、基本料金で5万円から8万円前後です。
交渉する内容によって別途料金が必要な場合が多いです。
また、退職金・慰謝料・残業代などの金銭請求では成功報酬として回収額の20%前後の報酬がかかるのが一般的です。
これは弁護士事務所によって違いますから、必ず料金を確認しておいてください。
スムーズに行って基本料金で済むケースもあれば、訴訟が絡むと総額15万円から20万円になることもあると聞いています。
安い料金ではありませんが、一般的な民事訴訟を弁護士に依頼すると安くても数十万円かかることを考慮すれば、妥当な金額と言っていいのかもしれません。
ただし、交渉事はすべてほぼ完全に行ってもらえます。
料金は銀行振り込みによる前払いが一般的です。クレジットカードが使用できるところもあります。
退職交渉の成功率は当サイトに掲載している退職代行サービスは100%です。万一退職がうまくいかなかった場合は返金保証があります。
労働組合が行う退職代行サービス
労働組合が行う退職代行サービスの利用は、弁護士に依頼したほうがいい事案がない場合に行います。
労働組合が行う退職代行サービスで対応可能なケースも多いと思います。
ただし、自衛隊員は労働組合に加入できない(自衛隊法64条)ので、労働組合が運営する退職代行を利用することは違法になりますので、必ず弁護士の退職代行を利用してください。
また、国家公務員のうち警察職員、海上保安庁職員、刑事施設において勤務する職員、 自衛隊員、そして地方公務員のうち警察職員、消防職員は労働組合に加入できません。(国家公務員法第108条の2第5項、自衛隊法第64条第1項、地方公務員法第52条第5項)これらの職員が退職代行を利用する際は弁護士の退職代行しか利用できないのでご注意ください。

労働組合の退職代行サービスの内容
次の一覧をご覧ください。
| 項目 | 労働組合が行う退職代行 |
| 退職意思を伝える | 〇 |
| 会社との細かな連絡調整 | △ 細かな調整は難しいかも |
| 退職書類の作成 | △ 労働組合側で用意した様式の場合が多い |
| 業務の細かな引継ぎ調整 | △ 細かな調整は難しいかも |
| 有給休暇の消化 | 〇 |
| 退職日の調整 | 〇 |
| 私物の引き取り・貸与品の返却 | 〇 |
| 残業代の請求 | △ 労働組合によります |
| 未払い金の請求 | △ 労働組合によります |
| 退職金の請求 | △ 労働組合によります |
| 慰謝料(損害賠償)の請求 | × 対応不可 |
| 訴訟の対応 | × 対応不可 |
| 転職サポート | 〇 対応しているところが多い |
労働組合の退職代行は、細かな調整をどこまでやってくれるかは依頼する労働組合によります。
言うのは得意ですが細かな調整は苦手のことがあります。
弁護士による退職代行サービスよりはきめ細かさでは弱いかもしれません。
特に話がうまくいかず訴訟になりそうなときは労働組合では対応できません。
やはり事前にどこまで対応ができるのか、伝えるだけなのかを把握しておくことは大事だと思います。
労働組合の退職代行サービスの料金
労働組合が行う退職代行サービスの料金相場は、2万円から3万円前後です。多くの場合は後払い可です。
特に別途料金は必要ありませんが、交渉を依頼する内容によって別途料金が必要かどうかは確認してください。
価格差を考えれば、初めから弁護士による退職代行サービスを利用するのもありかと思います。
退職交渉の成功率は当サイトに掲載している退職代行サービスは100%です。万一退職がうまくいかなかった場合は返金保証があります。
退職代行サービスの依頼から退職までの流れ
退職代行サービスの依頼から退職までの流れの概要です。

1.退職代行サービスサイトで内容をよく見てみる。知りたいことを問い合わせる
まずはサイトをよく見てみましょう。
何を代行してもらえるのか、料金はいくらか、別途料金はかかるのか、内容をよく確認しましょう。
メールやLINEで知りたいことを質問してみる。
どのようなシステムなのか。
明日会社に行かなくていいと書いてあっても事前に打ち合わせなどが必要な場合があります。
有給休暇をすべて消化できるのか。
離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票など、必要書類の受け取りはどうなるのか。
引継ぎなどの対応の仕方。
返す貸与品と自分の持ち物の引き取り方法。
料金。先払いか後払いか。別途料金が必要か。
支払い方法は。クレジット払い、コンビニ払いなど。
特に依頼できる内容と料金を良く把握しておくことが大事ですから、納得できるまで話をしましょう。
2.質問や説明に納得できれば正式に依頼する
料金は一般的に先払いですが、後払いもできる場合もあります。
3.業者が依頼者の代理人(民法上の正式な代理人)として会社に退職の連絡をする。
退職代行サービス業者が、依頼者の代理人として会社に退職の意思を伝え、有給休暇の取得や給与の支払い、離職票、雇用保険などの事務処理手続きを会社に依頼する。
4.会社に退職届を郵送する。貸与品がある場合は一緒に送る。
退職届を会社へ郵送すれば退職手続きが完了します。
料金後払いの時は料金の支払い。
手続き書類などの受領。
まずは、知りたいことを問い合わせてみましょう。
退職は法令上必ずできます。
退職代行を頼んだら、そこからは一切会社とやり取りしなくていいので安心です。
他社と比較検討する時間が欲しいときは、内容を検討したいからと伝えていったん電話を切っても構いません。
なお、ハラスメントを受けているなどの場合で、慰謝料の請求などを弁護士に依頼する場合は、その内容についてきちんとした打ち合わせが必要になります。電話可。
24時間対応。あすから出社不要の退職代行はこちらです
労働組合と弁護士事務所の退職代行サービスをご紹介します。以下はスポンサーリンクです。
1.女性の退職代行サービス【わたしNEXT】
女性の退職代行サービス【わたしNEXT】
一般社団法人日本退職代行協会(JRAA)の特級認定会員(正会員)となっていますから、信頼性の高い退職代行サービスです。
こちらは必ずしも女性に特化しているわけではないので、男性でも利用可能とのことです。
運営:労働組合
最短即日退職:可能
退職成功率:100%
転職サポート:完全無料
創業20年
6万件以上の実績
万一退職できなかった場合:100%返金保証
料金
◆正社員・契約社員・派遣社員・内定辞退・休職など:25,800円(税込)
※アルバイト・パート以外または社会保険に加入している方は(組合費別途¥1000)
◆アルバイト・パート(社会保険未加入):18,800円(税込)
※アルバイト・パートの方で社会保険に入っていない方は(組合費別途¥1000)
問い合わせは24時間対応
全国対応:OK
依頼できる雇用形態:正社員、派遣、パート、アルバイト
2.男性の退職代行依頼サービス【男の退職代行】
男性の退職代行依頼サービス【男の退職代行】
一般社団法人日本退職代行協会(JRAA)の特級認定会員(正会員)となっていますから、信頼性の高い退職代行サービスです。
こちらは男性の退職を専門に取り扱っておりますので、男性の方のみご依頼いただけます。女性の退職代行は女性の退職代行サービス【わたしNEXT】を利用してください。
運営:労働組合
最短即日退職:可能
退職成功率:100%
転職サポート:完全無料
創業20年
6万件以上の実績
万一退職できなかった場合:100%返金保証
料金
◆正社員・契約社員・派遣社員・内定辞退・休職など:25,800円(税込)
※アルバイト・パート以外または社会保険に加入している方は(組合費別途¥1000)
◆アルバイト・パート(社会保険未加入):18,800円(税込)
※アルバイト・パートの方で社会保険に入っていない方は(組合費別途¥1000)
問い合わせは24時間対応
全国対応:OK
依頼できる雇用形態:正社員、派遣、パート、アルバイト
3.弁護士法人みやび
弁護士法人みやび
最短即日退職:可
依頼当日は出社しなくていいか:OK
運営:弁護士法人みやび
◆料金:55,000円(税込)
※業務委託、自衛隊、会社に借り入れがある方(返済交渉込み)は77,000円(税込)
※パート・会社員・契約社員など27,500円(税込)
※成功報酬は残業代・退職金請求などの回収額の20%。ただし会社が支払いを拒否し弁護士が交渉を行った場合にのみ発生します。
銀行振込・クレジットカード払いOK
全国対応:OK
依頼できる雇用形態:正社員、公務員、派遣、パート、アルバイト
4.弁護士法人ガイア総合法律事務所
弁護士法人ガイア総合法律事務所
最短即日退職:可
依頼当日は出社しなくていいか:OK
運営:弁護士法人ガイア総合法律事務所
◆料金:55,000円(税込)
※業務委託、自衛隊、会社に借り入れがある方(返済交渉込み)は77,000円(税込)
※残業代、退職金請求は、別途成功報酬20%~30%が必要です。
銀行振込のみ
全国対応:OK
依頼できる雇用形態:正社員、派遣、パート、アルバイト
5.弁護士ビーノ
弁護士ビーノ
最短即日退職:可
依頼当日は出社しなくていいか:OK
運営:弁護士法人mamori
◆料金:66,000円(税込)
クレジットカード決済OK
全国対応:OK
依頼できる雇用形態:正社員、派遣、パート、アルバイト